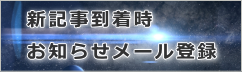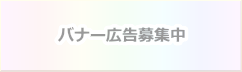ビジネストレンドのおまとめサイト ビジトレ!
特集!「生きものばんざい!身近な最先端」
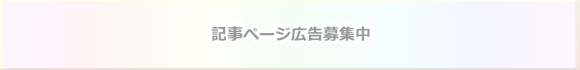
生きものばんざい!身近な最先端〜バイオミメティクス=生きものたちが最先端の先生!〜 皆さんの周りにあるスマートフォンやテレビ、飛行機や新幹線といったすごい技術は、すべて人間がゼロから考え出したものだと思っていませんか? それは、自然界に生きる生き物たちです。 何億年という気の遠くなるような長い時間をかけて、地球の厳しい環境を生き抜くために進化してきた生き物たち。彼らの体や能力には、私たちが抱える問題を解決するための、驚くべきヒントがたくさん詰まっています。
その答えはすべて、生き物たちが持っているスーパーパワーにあります。 このように、**生物(Bio)の構造や機能を模倣(Mimic)**して、新しい技術を生み出したり、ものづくりに活かしたりする考え方のことを「バイオミメティクス(Biomimetics)」や「生物模倣技術」と呼びます。 この記事では、そんなバイオミメティクスの世界を探検します。虫や動物、さらには植物たちが、いかにして私たちの生活を豊かにする最先端技術の「先生」になったのか。中学生の理科の授業のように、ワクワクする発見の旅に出かけましょう! 第1章:虫たちの小さな体は、アイデアの宝箱まずは、私たちの身近にいる小さな虫たちから見ていきましょう。ちょっと厄介者だと思われがちな彼らですが、その体には驚くべきテクノロジーが満載です。 ①【蚊の針 × 痛くない注射針】~チクッとしない秘密は「ギザギザ」にあった~夏の夜、私たちの睡眠を妨げる蚊。でも、刺された瞬間に「痛い!」と感じることは少なく、後からかゆくなって気づくことがほとんどですよね。これって、不思議だと思いませんか? その秘密は、蚊が持つ**口針(こうしん)**という、ストローのような細い針の構造にあります。蚊の針は、実は1本ではなく、数本の細かな針が束になってできています。そして、その針の先端は、ただ尖っているのではなく、ギザギザのノコギリ刃のような形をしています。 蚊は、このギザギザの針を小刻みに振動させながら、皮膚との接触面積を最小限にして、ゆっくりと刺していきます。だから、私たちの皮膚にある痛みを感じるセンサー(痛点)への刺激が少なく、刺されたことに気づきにくいのです。 この仕組みにヒントを得て開発されたのが、「痛くない注射針」です。日本の医療機器メーカーは、蚊の針を徹底的に研究し、先端がギザギザになった極細の注射針を開発しました。この針を使うと、従来の注射針に比べて痛みが大幅に軽減されるため、特に注射が苦手な子どもたちや、毎日インスリン注射が必要な糖尿病患者さんたちの大きな助けになっています。 蚊の「嫌われる能力」が、医療の現場で人々の苦痛を和らげる技術に変わった、素晴らしい例です。 ②【トンボの目 × 超高性能センサー】~グルグル回っても目が回らない!?360°見える驚異の複眼~空中を猛スピードで飛び回り、小さな虫を正確に捕まえるトンボ。彼らが名ハンターでいられる理由の一つは、その大きな目にあります。 トンボの目は「複眼(ふくがん)」と呼ばれ、数万個もの小さなレンズ(個眼)が集まってできています。私たち人間の目は、2つのレンズで物を見ていますが、トンボは数万個のレンズで、まるでモザイクアートのように世界を見ています。 この複眼のおかげで、トンボはほぼ360°の広い視野を持つことができます。さらに、それぞれのレンズが少しずつ違う角度を向いているため、獲物との距離や動きを非常に正確に捉えることができるのです。また、高速で飛んだり、急旋回したりしても、景色が流れて見えて目が回るということがありません。 このトンボの複眼の仕組みは、様々なセンサー技術に応用されています。
トンボのように「たくさんの目で同時に見る」というアイデアが、私たちの安全を守る技術に繋がっているのです。 ③【ハエの羽 × 高効率な小型ドローン】~省エネで力持ち!小さな羽ばたきの大きな可能性~ブーンと飛び回るハエ。彼らの飛行能力は、実は航空力学の専門家も驚くほど高度なものです。 飛行機やヘリコプターは、固定された翼や回転するプロペラで揚力(浮き上がる力)を得ます。しかし、ハエは薄くて軽い羽を巧みに羽ばたかせることで、空中に静止(ホバリング)したり、急旋回したり、後ろ向きに飛んだりといったアクロバティックな飛行をいとも簡単にやってのけます。 研究によると、ハエはただ羽を上下させているだけではありません。羽をひねるように回転させることで、小さな渦を発生させ、それを翼の上に留めることで、体のサイズからは考えられないほど大きな揚力を生み出していることが分かってきました。この飛行方法は、飛行機などに比べて非常にエネルギー効率が良いことも特徴です。 このハエの羽ばたきのメカニズムは、**次世代の小型ドローン(マイクロドローン)**の開発に大きなヒントを与えています。災害現場での人命捜索や、狭い場所の点検作業など、プロペラ式のドローンでは入れないような場所での活躍が期待されています。昆虫サイズのドローンが、瓦礫の隙間をスイスイと飛んでいく。そんなSF映画のような未来も、そう遠くないかもしれません。 ④【ホタルの光 × 省エネLED照明】~冷たい光の不思議!生物発光の仕組みを応用~夏の夜を彩るホタルの優しい光。触っても熱くない、あの不思議な光はどうやって生まれるのでしょうか? 私たちが普段使っている電球は、電気の力でフィラメントという金属線を熱して光らせるため、エネルギーの多くが熱として逃げてしまいます。しかし、ホタルの光は「生物発光」という化学反応によるもので、熱をほとんど出しません。 ホタルの体内にある「ルシフェリン」という物質が、「ルシフェラーゼ」という酵素の働きで酸素と結びつくときに光を放ちます。この反応は、エネルギーを光に変える効率が非常に高く、約90%以上という驚異的な数値を誇ります。白熱電球の変換効率が10%程度なのと比べると、そのすごさが分かりますね。 この「化学エネルギーを直接光に変える」というホタルの仕組みは、私たちの照明技術、特にLED照明の開発に大きな影響を与えました。LEDも、電気を直接光に変える半導体を使った技術であり、熱の発生が少なく、エネルギー効率が非常に高いのが特徴です。ホタルの発光メカニズムを研究することで、より効率の高いLED材料の開発が進められています。 自然界が生んだ究極の省エネ照明が、私たちの暮らしを明るく、そしてエコにしてくれているのです。 ⑤【蛾の目 × 反射しないディスプレイ】~夜のハンターの目は、なぜ光らない?モスアイ構造の秘密~夜に活動する蛾。彼らの目は、暗闇の中でわずかな光も逃さずに捉える必要があります。しかし、もし自分の目が光を反射してキラリと光ってしまったら、天敵に見つかってしまいますよね。 そうならないように、蛾の目(複眼)の表面には、とても不思議な構造があります。それは、光の波長よりも小さな、ナノレベル(1ミリの100万分の1)の微細な凹凸が、規則正しくびっしりと並んでいる構造です。 光がこの凹凸に当たると、屈折率が連続的に変化するため、光は反射されずにスムーズに目の中へと吸収されていきます。これが、蛾の目が暗闇で光らない理由です。この構造は「モスアイ(Moth-eye)構造」と呼ばれています。 このモスアイ構造を応用したのが、スマートフォンの画面やテレビのディスプレイ、カメラのレンズなどに使われている「無反射フィルム」です。画面に自分の顔や照明が映り込んで見えにくい、という経験はありませんか?モスアイ構造を持つフィルムを貼ることで、光の反射を極限まで抑え、明るい場所でも画面がくっきりと見えるようになります。 太陽光パネルの表面に応用すれば、反射によるエネルギーロスを減らし、発電効率を上げることもできます。蛾が天敵から身を守るための知恵が、私たちの「見やすさ」を支えるハイテク技術になっているのです。 第2章:動物たちの生きる知恵と驚きの身体能力次に、もう少し大きな動物たちの世界を見てみましょう。彼らのダイナミックな動きや驚異的な身体能力には、工学的な問題を解決するヒントが満載です。 ⑥【ヤモリの足 × 何でもくっつくテープ】~落ちない!剥がせる!魔法のテープのヒントは足の裏の毛~ヤモリは、ガラスのようなツルツルの壁や天井でも、まるで重力がないかのようにスルスルと歩き回ることができます。しかも、足の裏にネバネバした粘液を出しているわけではありません。 その秘密は、ヤモリの足の裏にあります。ヤモリの指の裏には、目に見えないほど細い**剛毛(ごうもう)**がびっしりと生えています。そして、その毛の先端はさらに数百本に枝分かれしています。 この無数の毛の先端が壁の表面の分子に近づくと、「ファンデルワールス力」という、すべての物質の間に働く非常に弱い引力が発生します。毛1本あたりの力はごくわずかですが、何億本もの毛先が同時に働くことで、ヤモリは自分の体重を余裕で支えるほどの強力な接着力を得ることができるのです。 そして、足を剥がすときは、毛の角度を少し変えるだけで、このファンデルワールス力を簡単に断ち切ることができます。だから、強力にくっつくのに、跡を残さずキレイに剥がせるのです。 このヤモリの足の仕組みを模倣して、何度も貼って剥がせる強力な粘着テープや、手術で臓器を傷つけずに持ち上げるための医療器具などの開発が進められています。未来のレスキューロボットは、ヤモリのように壁を登って、人を助けに行くかもしれません。 ⑦【カワセミのくちばし × 新幹線の静かな走り】~速くて静か!トンネル突入音を消した鳥のくちばし~日本の技術の象徴でもある新幹線。しかし、その開発の歴史の中には、ある大きな悩みがありました。それは、高速でトンネルに突入する際に発生する「トンネル微気圧波」という現象です。 電車がトンネルに入ると、中の空気が圧縮されて衝撃波となり、トンネルの出口で「ドーン!」という大きな騒音を発生させてしまいます。この騒音は、沿線の住民にとって大きな問題でした。 この問題を解決したのが、なんと「カワセミ」という鳥です。カワセミは、空中から水中にいる魚を捕らえるハンターです。高速で水に飛び込むときに、ほとんど水しぶきを立てません。これは、カワセミの長くて鋭いくちばしが、水の抵抗を最小限に抑える理想的な形をしているからです。 このカワセミのくちばしの形にヒントを得て、当時の500系新幹線の先頭車両は、流線形のデザインに改良されました。その結果、トンネル突入時の空気抵抗が劇的に減少し、騒音問題が解決されただけでなく、消費電力も削減され、さらにスピードアップまで実現したのです。 自然界のハンターの美しいフォルムが、日本の高速鉄道の進化に大きく貢献した、非常に有名なエピソードです。 ⑧【サメの肌 × 汚れにくい水着と飛行機】~水の抵抗を減らし、菌も寄せ付けないザラザラの肌~海の王者、サメ。彼らはなぜあんなに速く泳げるのでしょうか?その秘密の一つは、肌の表面にあります。 サメの肌は、触るとヤスリのようにザラザラしています。これは、リブレットと呼ばれる、進行方向と平行に並んだ微細な溝構造で覆われているからです。この溝が、泳ぐときに水の流れを巧みにコントロールし、水の抵抗を最大で**約10%**も減少させることが分かっています。 この「サメ肌(シャークスキン)」の構造は、様々な分野で応用されています。
サメの肌は、速く泳ぐだけでなく、体を清潔に保つための知恵でもあったのです。 ⑨【ハコフグの形 × 燃費の良い自動車】~四角いのにスムーズ!?空気抵抗が少ない不思議なボディ~海の魚であるハコフグ。その名の通り、箱のように四角くて、お世辞にも速く泳げそうな形には見えません。しかし、驚くことに、ハコフグの体は非常に水の抵抗が少ないことが分かっています。 ハコフグの体の表面にある六角形のウロコや、角張ったボディラインが、体の周りに発生する水の渦をうまくコントロールし、流れをスムーズにすることで、抵抗を減らしているのです。また、この箱型の骨格は、外敵から身を守るための鎧としても機能しており、非常に頑丈です。 ドイツの自動車メーカー、メルセデス・ベンツは、このハコフグの形に注目しました。「空気抵抗が少なく、かつ車内空間を広く確保でき、さらにボディ剛性も高い」という、自動車の理想を体現していると考えたのです。 そして、ハコフグをモデルにしたコンセプトカーを開発したところ、当時の同じサイズの車と比べて、空気抵抗を大幅に削減し、20%以上も燃費を向上させることに成功しました。一見すると奇妙に見える自然界のデザインに、優れた機能性が隠されていることを証明したのです。 ⑩【クモの糸 × 鉄より強い夢の繊維】~細くて軽くて、ものすごく丈夫!未来を変えるクモの糸~クモの巣に使われているクモの糸。細くて頼りなく見えますが、実はとんでもないスーパー繊維です。 クモの糸は、同じ太さの鋼鉄(鉄)と比べると約5倍もの強度を持ち、ナイロンよりもはるかに伸縮性があるという驚異的な性質を持っています。それでいて、主成分はタンパク質なので、最終的には土に還る環境に優しい素材です。 もし、このクモの糸を人工的に大量生産できたら、私たちの社会は大きく変わるかもしれません。
しかし、クモは肉食で共食いをしてしまうため、カイコのように家畜化して糸を大量生産することができません。そこで、日本のベンチャー企業などが中心となり、クモの糸の遺伝子を微生物に組み込んで、発酵によって人工的にクモの糸のタンパク質を作り出すという研究が進められています。すでに、この人工クモ糸を使ったアウトドアジャケットなどが製品化されており、夢の繊維の実用化は、もう目の前まで来ています。 第3章:植物や見えない生き物も先生だ!最後に、動物だけでなく、植物や小さな生き物たちから学んだ技術も見てみましょう。 ⑪【ハスの葉 × 絶対に濡れないコーティング】~水をコロコロ弾く!泥も汚れも寄せ付けない葉っぱの表面~ハスの葉の上に落ちた水滴が、濡れ広がらずにコロコロとした玉になって転がり落ちていくのを見たことがありますか?この現象を「ロータス効果」と呼びます。 ハスの葉の表面を拡大して見ると、実はツルツルではなく、目に見えないミクロ(1ミリの1000分の1)レベルの凹凸があり、さらにその表面がワックスのような撥水(はっすい)性の物質で覆われています。 この微細な凹凸のおかげで、水滴は葉の表面に直接触れることができず、空気の層の上に乗っかっているような状態になります。だから、球形のままコロコロと転がることができるのです。そして、水滴が転がるときに、葉の上のホコリや泥といった汚れをくっつけて一緒に取り去ってくれます。これが、ハスの葉がいつもキレイな理由です。 このロータス効果は、水を弾き、汚れを防ぐ技術として、様々な製品に応用されています。
⑫【カタツムリの殻 × いつもキレイな外壁】~雨が降るたびにピカピカに!セルフクリーニングの秘密~雨上がりに、カタツムリを見かけると、その殻はいつもピカピカですよね。実は、カタツムリの殻にも、汚れを寄せ付けないハイテクな仕組みが隠されています。 カタツムリの殻の表面には、非常に細かい溝がらせん状に刻まれています。そして、その表面はとても**水に馴染みやすい(親水性)**性質を持っています。 油汚れのようなものが殻に付着しても、殻と汚れの間に水が入り込みやすい構造になっているため、雨が降ると、水が汚れを浮かび上がらせ、そのまま洗い流してくれるのです。これを「セルフクリーニング効果」と呼びます。 この仕組みは、住宅の外壁タイルなどに応用されています。表面にカタツムリの殻のような親水性の高いコーティングを施すことで、排気ガスなどの油汚れが付着しても、雨水がその汚れを洗い流してくれます。つまり、雨が降るたびに、壁が自動的にキレイになるのです。面倒な窓拭きや壁の掃除の手間を省いてくれる、主婦(主夫)の味方とも言える技術ですね。 おわりに:自然に学び、未来を創る「バイオミメティクス」ここまで、様々な生き物たちの驚くべき能力と、そこから生まれた最先端技術の数々を紹介してきました。
私たちの周りにある便利なモノたちが、実はたくさんの生き物たちの知恵と工夫の賜物であることが、お分かりいただけたでしょうか。 バイオミメティクスという分野が教えてくれる最も大切なことは、「自然は、人類にとって最高の教科書である」ということです。38億年という長い生命の歴史の中で、生き物たちは試行錯誤を繰り返し、エネルギーを無駄にせず、環境に負荷をかけない、持続可能な方法で生きる術を身につけてきました。 私たちが今、地球温暖化やエネルギー問題といった大きな課題に直面している中で、この自然から学ぶという姿勢は、ますます重要になっています。 この記事を読んでいただいた皆さんも、ぜひ身の回りの生き物たちを、これまでとは少し違う目で観察してみてください。「どうして、この虫はこんな形をしているんだろう?」「この植物の葉っぱは、なぜこんなにツルツルなんだろう?」そんな素朴な疑問や好奇心の中に、未来の世界をより良くするための、素晴らしいアイデアの種が隠されているかもしれません。 私たちの先生は、すぐそこにいるのですから。 「ビジトレ!」編集部 |